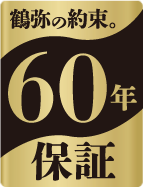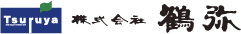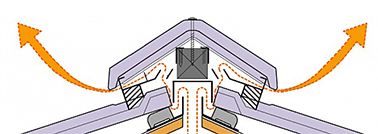スタッフブログ
カレンダー
最近のエントリー
2025/04/18NEWS
第7回 鶴弥全社改善発表大会が開催されました
2025/04/14
日本最古の駅舎
2025/04/07NEWS
当社の桜並木(4月7日)
2025/04/01
ブログ大賞
2025/03/31
梅まつり
2025/03/28
mediasエリアニュース で放映されました
2025/03/24
【テレビ放映のお知らせ】mediasエリアニュース 3月27日(木)17:00~
2025/03/24
ホスピタリティ
2025/03/17
春の定義
2025/03/03
石川県の建物の特徴
2022/01
24(月)

こんにちは。
鶴弥 製造技術部金型課の長妻です。
タイトルを見て防災J形瓦 エースを思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。
今回は瓦のエースではなく、金型課のエースを追って
金型課の仕事についてチラッと紹介したいと思います!!
金型課エースのお仕事紹介

兄貴的存在でみんなに頼られていますが、こうしたエプロン姿だと、お母さんにすら見えてきますね。
左:金型課エース(山本) 中:防災J形瓦エース 右:エース製造ライン長(河部)

彼の1日は製品の点検から始まります。
工場内の各ラインの製品をチェックし、納めた金型で成形して最終的に出来上がった製品に異常がないか確認します。
左:最近、購入したワイヤレスイヤホンが届きご機嫌(山本)
右:彼女募集中の26歳(鳥居)

鋭い眼光でチェック!!
成形を繰り返すと金型が摩耗し、瓦の端部にバリが立ってきます。

バリを修正し、良好な状態で成形出来るよう金型を維持する事も金型課の仕事となります。

修正後の状況を確認し、ラインの班長と意見交換しています。
(ガンプラ仲間だからひょっとしたらガンプラについて話しているのかも…‼)
【好きなガンプラ】左(山本):「Hi-νガンダム」 右(班長):「ジオング」

現場での修正も行いますが、作業の大半は次の成形に向け、戻って来た金型をメンテナンスする作業になります。

何やら後輩に熱く指導しています。
こうした情熱を持った人たちに支えられて金型・製品は作られています。
2022/01
17(月)
今回は陶板壁材スーパートライWallが取得している防耐火認定についてのお話です!
まず防耐火認定とは何でしょうか?
建物が密集している都市部で火災が発生した場合の被害を最小限にするために、都市計画法で定められている防火地域に建てられる所定の建築物は、一部の条件を除いて耐火建築物にする必要があリます。
用途地域、建物の階高、延床面積などによって耐火建築物にするか準耐火建築物にするかの建築条件が変わってきます。
大きな建物になるほど、耐火性能を確保するために耐火建築物にする必要が出てきます。
「陶板壁材スーパートライWall プレーン・ワイドボーダー」は壁の防耐火構造について以下の認定を取得しています。
①木造軸組工法 30分防火構造
②木造軸組工法 45分準耐火構造
③木造枠組壁工法 30分防火構造
④鉄骨下地 1時間耐火構造(非耐力)
例えば②木造軸組工法 45分準耐火構造の認定があると防火地域(駅前など、火災に対して厳しい制約がある地域)であっても、2階建てで延床面積100㎡以下の木造住宅であれば「陶板壁材スーパートライWall」を使って建築することができます。
2022/01
06(木)
鶴弥 総務部です!!
鶴弥では毎年、新年の業務初日に、「仕事始め式」が執り行われます。
本日1/6(木)、2022年仕事始め式を開催いたしました!!
昨年は新型コロナウイルスの影響でオンラインでの仕事始め式でした。
今年も感染症対策のため、参加人数を制限しての開催となりました!
仕事始め式では、
社長の年頭挨拶や各表彰(永年勤続者・改善提案・無事故無災害・5S年間優秀)を行います。
永年勤続表彰は、勤続30年、25年、20年、15年、10年の社員が対象です。
今年の永年勤続表彰の対象者は80名!! (担当者曰く、ここ数年で一番多いとのこと! ('O'*) )
鶴弥は、こんなにも多くの人が"長く”勤めることのできる会社です。
そんな鶴弥では、おうちの美観を”長く”保つことのできる防災瓦や陶板壁材を製造しています。
本年も株式会社鶴弥をよろしくお願いいたします。
仕事始め式の様子

社長年頭挨拶

特別表彰

永年勤続代表者 謝辞
2021/12
27(月)
2021/12
20(月)
こんにちは、鶴弥 経理室です!!

さて突然ですが、日本で使われている瓦の起源はいつごろなのか知っていますか?

日本に瓦が入ってきたのは、今から約1400年前の西暦588年以降とされており、中国を起源として朝鮮半島を渡ってやってきました。
では、中国で瓦が造られるようになったのはいつなのでしょうか?
これまでの定説では、中国の陝西省宝鶏市岐山県鳳雛村にある西周時代の周原遺跡から出土したものが最古であり、紀元前11世紀ごろ、現在からおよそ3000年前とされていました。
中国の陝西省歴史博物館(陝西省西安市)で展示されている、発掘された同時代の瓦です(色の濃い部分)。コロナ前に実際に見に行ってきました。すでにいくつかの模様が施されているのがわかります。(クリックすると拡大します)
ところが、西暦2000年ごろからの最新の発掘調査で、なんと紀元前15世紀以前の殷(商)時代の遺跡(河南省鄭州市の二里岡遺跡)からも瓦が発見されるようになってきました。
このため現在では、瓦の起源は、最低でも現在から3500年前まで遡れると考えられるようになってきています。 (研究者によっては4000~5000年前と主張される方もいます)

ちなみに、そのころの日本は縄文時代の後期にあたります。
こんなに昔から、人々は瓦を屋根に使うことの有効性に気づいていたんですね。
もちろん今では、その当時よりも製造技術が発達し、形状や色もバリエーション豊かになっていますが、焼き物のもつ耐久性を屋根に生かすという発想は大昔から変わることなく引き継がれています。
ご自宅の新築・改築等をお考えの方は、是非、3500年の実績と信頼の瓦をご検討下さい。
このブログを書くにあたって参考にさせていただきました。
・愛知県陶器瓦工業組合ホームページ
・大脇 潔 先生 ご講演
・東の造瓦ことはじめ(アジア地域研究) 著者:中村 亜希子 氏